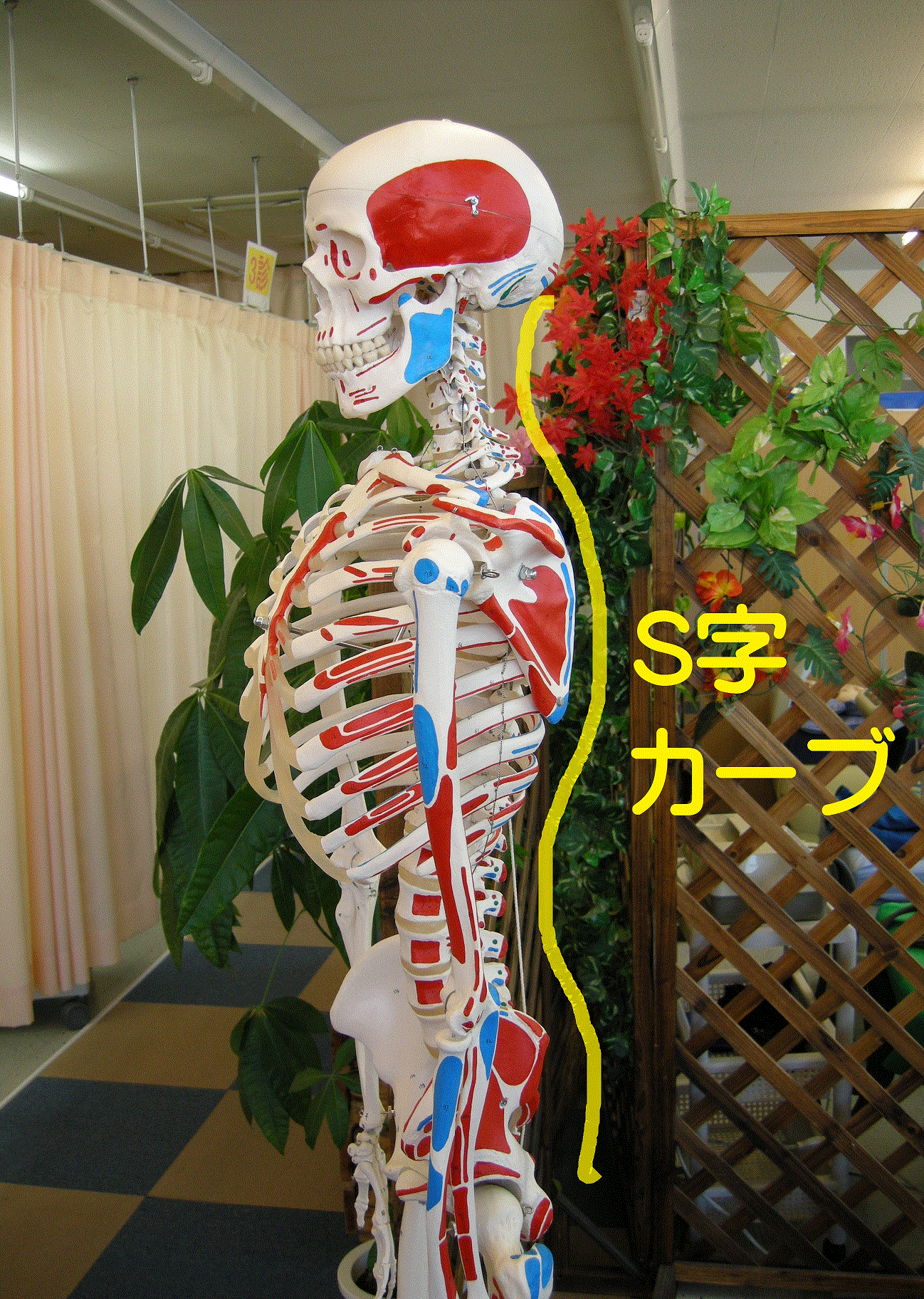◆『21世紀に生きる君たちへ』
司馬遼太郎
私は歴史小説を書いてきた。
もともと歴史が好きなのである。両親を愛するようにして、歴史を愛している。
歴史とは何でしょう、と聞かれるとき、
「それは、大きな世界です。かつて存在した何億という人生がそこにつめこまれている世界なのです。」
と、答えることにしている。
私には、幸い、この世にたくさんのすばらしい友人がいる。
歴史の中にもいる。そこには、この世では求めがたいほどにすばらしい人たちがいて、私の日常を、はげましたり、なぐさめたりしてくれているのである。
だから、私は少なくとも2千年以上の時間の中を、生きているようなものだと思っている。
この楽しさは、・・・・もし君たちさえそう望むなら・・・・おすそ分けしてあげたいほどである。
ただ、さびしく思うことがある。
私が持っていなくて、君たちだけが持っている大きなものがある。未来というものである。
私の人生は、すでに持ち時間が少ない。例えば、21世紀というものを見ることができないに違いない。
君たちは、ちがう。
21世紀をたっぷり見ることができるばかりか、そのかがやかしいにない手でもある。
もし「未来」という町角で、私が君たちをよびとめることができたら、どんなにいいだろう。
「田中君、ちょっとうかがいますが、あなたが今歩いている21世紀とは、どんな世の中でしょう。」
そのように質問して、君たちに教えてもらいたいのだが、ただ残念にも、その「未来」という町角には、私はもういない。
だから、君たちと話ができるのは、今のうちだということである。
もっとも、私には21世紀のことなど、とても予測できない。
ただ、私に言えることがある。それは、歴史から学んだ人間の生き方の基本的なことどもである。
昔も今も、また未来においても変わらないことがある。
そこに空気と水、それに土などという自然があって、人間や他の動植物、さらには微生物にいたるまでが、それに依存しつつ生きているということである。
自然こそ不変の価値なのである。なぜならば、人間は空気を吸うことなく生きることができないし、水分をとることがなければ、かわいて死んでしまう。
さて、自然という「不変のもの」を基準に置いて、人間のことを考えてみたい。
人間は・・・・繰り返すようだが・・・・自然によって生かされてきた。古代でも中世でも自然こそ神々であるとした。
このことは、少しも誤っていないのである。歴史の中の人々は、自然をおそれ、その力をあがめ、自分たちの上にあるものとして身をつつしんできた。
この態度は、近代や現代に入って少しゆらいだ。 ・・・・
人間こそ、いちばんえらい存在だ。という、思い上がった考えが頭をもたげた。
20世紀という現代は、ある意味では、自然へのおそれがうすくなった時代といってもいい。
同時に、人間は決しておろかではない。
思いあがるということとはおよそ逆のことも、あわせ考えた。つまり、私ども人間とは自然の一部にすぎない、というすなおな考えである。
このことは、古代の賢者も考えたし、また19世紀の医学もそのように考えた。
ある意味では、平凡な事実にすぎないこのことを、20世紀の科学は、科学の事実として、人々の前にくりひろげてみせた。
20世紀末の人間たちは、このことを知ることによって、古代や中世に神をおそれたように、再び自然をおそれるようになった。
おそらく、自然に対しいばりかえっていた時代は、21世紀に近づくにつれて、終わっていくにちがいない。
「人間は自分で生きているのではなく、大きな存在によって生かされている。」
と、中世の人々は、ヨーロッパにおいても東洋においても、そのようにへりくだって考えていた。
このかんがえは、近代に入ってゆらいだとはいえ、右に述べたように近ごろ再び、人間たちはこのよき思想を取りもどしつつあるように思われる。
この自然へのすなおな態度こそ、21世紀への希望であり、君たちへの期待でもある。
そういう素直さを君たちが持ち、その気分をひろめてほしいのである。
そうなれば、21世紀の人間はよりいっそう自然を尊敬することになるだろう。
そして、自然の一部である人間どうしについても、前世紀にもまして尊敬しあうようになるのにちがいない。
そのようになることが、君たちへの私の期待でもある。
さて、君たち自身のことである。
君たちはいつの時代でもそうであったように、自己を確立せねばならない。 ・・・・
自分に厳しく、相手にはやさしく。 という自己を。
そして、すなおでかしこい自己を。
21世紀においては、特にそのことが重要である。
21世紀にあっては、科学と技術がもっと発達するだろう。
科学・技術がこう水のように人間をのみこんでしまってはならない。
川の水を正しく流すように、君たちのしっかりした自己が科学と技術を支配し、よい方向に持っていってほしいのである。
右において、私は「自己」ということをしきりに言った。自己といっても、自己中心におちいってはならない。
人間は、助け合って生きているのである。
私は、人という文字を見るとき、しばしば感動する。斜めの画がたがいに支え合って、構成されているのである。
そのことでも分かるように、人間は、社会をつくって生きている。社会とは、支え合う仕組みということである。
原始時代の社会は小さかった。家族を中心とした社会だった。
それがしだいに大きな社会になり。今は、国家と世界という社会をつくりたがいに助け合いながら生きているのである。
自然物としての人間は、決して孤立して生きられるようにはつくられていない。
このため、助けあう、ということが、人間にとって、大きな道徳になっている。
助け合うという気持ちや行動のもとのもとは、いたわりという感情である。
他人の痛みを感じることと言ってもいい。
やさしさと言いかえてもいい。
「いたわり」
「他人の痛みを感じること」
「やさしさ」
みな似たようなことばである。
この三つの言葉は、もともと一つの根から出ているのである。根といっても、本能ではない。だから、私たちは訓練をしてそれを身につけねばならないのである。
その訓練とは、簡単なことである。
例えば、友達がころぶ。ああ痛かったろうな、と感じる気持ちを、その都度自分中でつくりあげていきさえすればいい。
この根っこの感情が、自己の中でしっかり根づいていけば、他民族へのいたわりという気持ちもわき出てくる。
鎌倉時代の武士たちは、
「たのもしさ」
ということを、たいせつにしてきた。人間は、いつの時代でもたのもしい人格を持たねばならない。
人間というのは、男女とも、たのもしくない人格にみりょくを感じないのである。
もう一度繰り返そう。さきに私は自己を確立せよ、と言った。自分に厳しく、あいてにはやさしく、とも言った。
それらを訓練することで、自己が確立されていくのである。そして、“たのもしい君たち”になっていくのである。
以上のことは、いつの時代になっても、人間が生きていくうえで、欠かすことができない心構えというものである。
君たち。君たちはつねに晴れあがった空のように、たかだかとした心を持たねばならない。
同時に、ずっしりとたくましい足どりで、大地をふみしめつつ歩かねばならない。
私は、君たちの心の中の最も美しいものを見続けながら、以上のことを書いた。
書き終わって、君たちの未来が、真夏の太陽のようにかがやいているように感じた。
◆『洪庵のたいまつ』
世のために尽くした人の一生ほど、美しいものはない。
ここでは、特に美しい生涯を送った人について語りたい。
緒方洪庵のことである。
この人は、江戸末期に生まれた。
医者であった。
かれは、名を求めず、利を求めなかった。
あふれるほどの実力がありながら、しかも他人のために生き続けた。そういう生涯は、はるかな山河のように、実に美しく思えるのである。
といって、洪庵は変人ではなかった。どの村やどの町内にもいそうな、ごく普通のおだやかな人がらの人だった。
病人には親切で、その心はいつも愛に満ちていた。
かれの医学は、当時ふつうの医学だった漢方ではなく、世間でもめずらしいとされていたオランダ医学(蘭方)だった。
そのころ、洪庵のような医者は、蘭方医とよばれていた。
変人でこそなかったが、蘭方などをやっているということで、近所の人たちから、
「変わったお人やな。」
と思われていたかも知れない。ついでながら、洪庵は大坂(今の大阪市)に住んでいた。
なにしろ洪庵は、日常、人々にとって見慣れない横文字(オランダ語)の本を読んでいるのである。
いっぱんの人から見れば、常人のようには思われなかったかもしれない。
洪庵は、備中(今の岡山県)の人である。
現在の岡山市の西北方に足守という町があるが、江戸時代、ここに足守藩という小さな藩があって、緒方家は代々そこの藩士だった。
父が、藩の仕事で大坂に住んだために、洪庵もこの都市で過ごした。
少年のころ、一人前のさむらいになるために、漢学の塾やけん術の同情に通ったのだが、生まれつき体が弱く、病気がちで、塾や道場をしばしば休んだ。
少年の洪庵にとって、病弱である自分が歯がゆかった。この体、なんとかならないものだろうかと思った。
人間は、人なみでない部分をもつということは、すばらしいことなのである。そのことが、ものを考えるばねになる。
少年時代の洪庵も、そうだった。かれは、人間について考えた。
人間が健康であったり、健康でなかったり、また病気をしたりするということは、いったい何に原因するのか。
さらには、人体というのはどういう仕組みになっているのだろう、というようなことを考え込んだ。
この少年は、ものごとを理づめで考えるたちだった。
今の言葉でいえば、科学的に考えることが好きだったといっていい。
少年は、蘭学特に蘭方医学を学びたいと思った。
幸い、この当時、中天遊(1783~1835)という学者が、大坂で蘭方医学の塾を開いていて、
あわせて初歩的な物理学や化学につても教えていた。
少年はここに入門した。主として医学を学んだのである。
中天遊からすべてを学び取った後、さらに師を求めて江戸へ行った。二十二才のときであった。
江戸では、働きながら学んだ。あんまをしてわずかな金をもらったり、他家のげんかん番をしたりした。
そのころ、江戸第一の蘭方医学の大家は、坪井信道(1795~1848)という人だった。
ついでながら、江戸時代の習慣として、えらい学者は、ふつうその自たくを塾にして、自分の学問を年わかい人々に伝えるのである。
それが、社会に対する恩返しとされていた。
洪庵は、坪井信道の塾で四年間学び、ついにオランダ語の難しい本まで読むことができるようになった。
そのあと、長崎へ行った。
長崎。
この町についてあらかじめ知っておかねばならないことは、江戸時代が鎖国だったことである。
幕府は、長崎港一カ所を外国に対して開いていた。
その外国も限られていて、アジアの国々では中国(当時は清国)だけであり、ヨーロッパの国々ではオランダだけだった。
そういうわけで、長崎にはオランダ人がごく少数ながら住んでいたのである。
もう少し鎖国について話したい。
鎖国というのは、例えば、日本人全部が真っ暗な箱の中にいるようなものだったと考えればいい。
長崎は、箱の中の日本としては、はりでついたように小さなあなだったといえる。
その小あなからかすかに世界の光が差しこんできていたのである。
当時の学問好きの人々にとって、その光こそ中国であり、ヨーロッパであった。
人々にとって、志さえあれば、暗いはこの中でも世界を知ることができる。
例えば、オランダ語を学び、オランダの本を読むことによって、ヨーロッパの科学のいくぶんかでも自分のものにすることができたのである。
洪庵もそういう青年の一人だった。洪庵は長崎の町で二年学んだ。
二十九才の時、洪庵は大坂にもどった。
ここでしんりょうをする一方、塾を開いた。
ほぼ同時に結こんもした。妻は、八重という、やさしくて物静かな女性だった。
考え深くもあった。八重は終生、かれを助け、塾の書生たちからも母親のようにしたわれた。
洪庵は自分の塾の名を適塾と名付けた。
日本のきんだいが大きなげき場とすれば、明治はそのはなやかなまく開けだった。
その前の江戸末期は、はいゆうたちのけいこの期間だったといえる。適塾は、日本の近代のためのけいこ場の一つになったのである。
すばらしい学校だった。 入学試験などはない。
どのわか者も、勉強したくて、遠い地方から、はるばるとやってくるのである。
江戸時代は身分差別の社会だった。しかしこの学校は、いっさい平等だった。
さむらいの子もいれば町医者の子もおり、また農民の子もいた。
ここでは、「学問をする」というただ一つの目的と心で結ばれていた。
適塾においては、最初の数年は、オランダ語を学ぶことについやされる。
先生は、洪庵しかいない。
その洪庵先生も、病人たちをしんりょうしながら教える。
体が二つあっても足りないほどいそがしかったが、それでも塾の教育はうまくいった。
塾生のうちで、よくできる者ができない者を教えたからである。
八つの級に分かれていて、適塾に入って早々の者は八級とよばれる。
一級の人は、最も古いし、オランダ語もよくできる。各級に、学級委員のように「会頭」という者がいる。
塾生全部の代表として、塾頭という者がいた。
ある時期の塾頭として、後に明治陸軍をつくることになる大村益次郎がいたし、
また別の時期の塾頭として、後に慶應義塾大学のそう立者になる福沢諭吉もいた。
適塾の建物は、今でも残っている。場所は、大阪市中央区北浜三丁目である。
当時、そのあたりは商家がのきをならべていて、適塾の建物はその間にはさまれていた。
造りも商家風で、今日の学校という感じのものではない。門もなければ運動場もなく、あるのは二階建てのただの民家だった。
その二階が塾生のね起き場所であった。そして教室でもあった。
塾生たちは、そこでひしめくようにしてくらしていた。夏は暑かったらしい。
先に述べた福沢諭吉は、明治以後、当時を思い出して、
「ずいぶん罪のないいたずらもしたが、これ以上できないというほどに勉強もした。
目が覚めれば本を読むというくらしだから、適塾にいる間、まくらというものをしたことがない。夜はつくえの横でごろねをしたのだ。」
という意味のことを述べている。
洪庵は、自分自身と弟子たちへのいましめとして、十二か条よりなる訓かいを書いた。
その第一条の意味は次のようで、まことにきびしい。
医者がこの世で生活しているのは、人のためであって自分のためではない。決して有名になろうと思うな。また利益を追おうとするな。ただただ自分をすてよ。そして人を救うことだけを考えよ。
そういう洪庵に対し、幕府は、
「江戸へ来て、将軍様の侍医(奥医師)になれ。」 ということを言ってきた。
目もくらむほどにめいよなことだった。奥医師というのは、日本最高の医師というだけでなく、その身分は小さな大名よりも高かったのである。
つまり、洪庵の自分へのいましめに反することだった。 洪庵は断り続けた。
しかし幕府は聞かず、ついに、いやいやながらそれにしたがった。
洪庵は五十三才のときに江戸へ行き、そのよく年、あっけなくなくなってしまった。
もともと病弱であったから、わかいころから体をいたわり続け、心もできるだけのどかにするよう心がけてきた。
ところが、江戸でのはなやかな生活は、洪庵の性に合わず、心ののどかさも失われてしまった。
それに新しい生活が、かれに無理を強いた。
それらが、かれの健康をむしばみ、江戸へ行ったよく年、火が消えるようにしてなくなったのである。
振り返ってみると、洪庵の一生で、最も楽しかったのは、かれが塾生たちを教育していた時代だったろう。
洪庵は、自分の恩師たちから引き継いだたいまつの火を、よりいっそう大きくした人であった。
かれの偉大さは、自分の火を、弟子たちの一人一人に移し続けたことである。
弟子たちのたいまつの火は、後にそれぞれの分野であかあかとかがやいた。
やがてはその火の群が、日本の近代を照らす大きな明かりになったのである。
後生のわたしたちは、洪庵に感謝しなければならない。